「部下にどうフィードバックすればいいのかわからない」「厳しく言うと関係が悪くなりそうだし、やさしすぎても響かない」――そんな悩みを抱えているマネージャーは多いのではないでしょうか。
結論から言うと、
良いチームをつくるためには、日常の小さなフィードバックを積み重ねることが不可欠です。
年に1回の評価面談や半期に一度の振り返りだけでは、メンバーの行動は変わりません。
日常の中で具体的な行動に光を当てていくことが、本人の成長を支え、
チーム全体のパフォーマンスを底上げするポイントになります。
このようなフィードバックを習慣化できれば、
実際、マネジメントの現場でも「小さなフィードバックが行動を変える」ことは繰り返し確認されています。心理学的にも、人は「行動直後のフィードバック」で学習効果が高まることがわかっています。
- メンバーが自信を持って動ける
- チームの目的に沿った行動が自然と増える
- マネージャー自身の負担も減り、組織が自走する
といったメリットが得られます。
そこで今回は、日常のフィードバックで行動を支える具体的な方法を解説していきます。
なぜ日常のフィードバックが重要なのか
評価や面談の場でまとめてフィードバックをしても、その時は本人も、
「頑張るぞ!」と思っても、なかなか継続的に意識はできないものです。
一方で、日常的に小さな行動に対してフィードバックがあると、
- 具体的な行動ベースで何が良いか、良くないかすり合わせができるので本人が実感を持ちやすい
- 望ましい行動が習慣化しやすく、望ましくない行動は振り返ってもらいやすい
といった効果が得られます。つまり、フィードバックは“行動のナビゲーション”なのです。
効果的なフィードバックの種類
次に、どんなフィードバックの種類があるのかをみて行きましょう。
承認(良い行動を見逃さない)
メンバーがチームの目的に沿った行動をした時は、小さくてもその場で承認します。
その際、ただ褒めるのではなく具体的に「どんな行動が」「なぜ良かったのか」を伝えます。
例:「会議でAさんに発言を促したの、場が広がって良かったね。ファシリのレベル上がってるよ」
修正(改善点を具体的に伝える)
改善点を伝えるときは、人格ではなく行動にフォーカスします。
行動を変えた結果、どういった影響があるのかも伝えてあげると納得感が増します。
例:「資料は要点を2枚にまとめられると、読み手の頭が整理されやすいよ」
期待(未来志向で背中を押す)
「次はこうしてほしい」という期待を、チーム全体の目的とつなげて伝えます。
例:「次の商談では、具体的な課題を深掘りできるとより地域に根付いた営業所に近づくよ」
フィードバックの実践ステップ
- 観察する:メンバーの行動を注意深く見る
- 具体的に言語化する:「〜が良かった」「〜を工夫するともっと良くなる」
- 即時に伝える:できるだけその場で声をかける
このサイクルを日常的に繰り返すことで、メンバーは「何をすれば良いか」を迷わずに動けるようになります。
やりがちなNGフィードバック
- 抽象的すぎる:「もっと頑張って」
- 人格否定に聞こえる:「なんでこんなこともできないの?」
- ジャッジだけで終わる:「これはダメ」
これらは本人のモチベーションを下げてしまい、行動の改善にはつながりません。
まとめ:小さな積み重ねが大きな行動変化に
日常のフィードバックは、メンバーの行動をナビゲートし、チームの目的に沿った動きを自然と引き出します。承認・修正・期待を意識して、日常的に小さな声かけを積み重ねていくことが、良いチームをつくる近道です。
「どう伝えればいいかわからない」という悩みを持つマネージャーこそ、まずは今日から一言でも承認のフィードバックを始めてみてください。きっとメンバーの行動が変わり、チームの空気も前向きに変わっていくはずです。
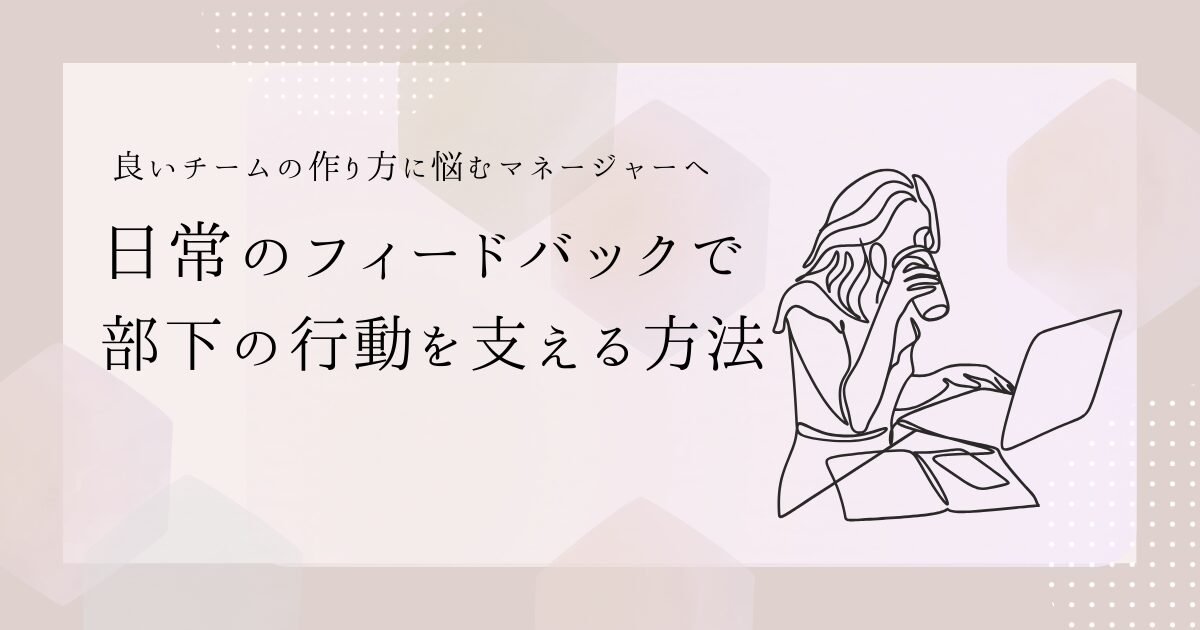
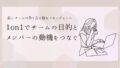
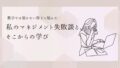
コメント